相模原市スポーツ協会より、優秀団体として表彰して頂きました
法政クラブを立ち上げて約10年
最初は少人数、初心者の子供たちから始まり、徐々に人数、練習場所が増えました
今日では全国大会に出場する選手もいます
これまでの取り組み、成果を評価して頂き、とても嬉しいです
練習に参加してくれる子ども達、保護者の方々のおかげでチームが成り立ちます
感謝しています(*^-^*)
次なる10年に向けてさらに飛躍していけるように頑張ります!!
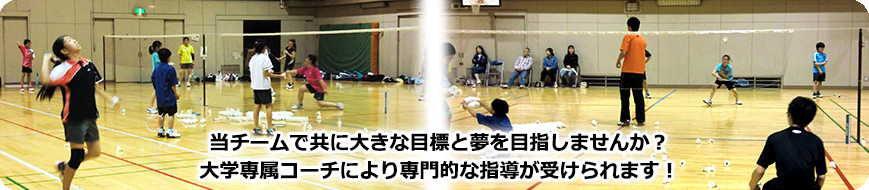
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 1月 | 3月 » | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
・3連休初日(土曜日)、アマノガワ主催の中学生練習会に参加させて頂きました
テスト空けだったので動けるか不安もありましたが、みんなちゃんと動けていて安心しました
参加させて頂き、ありがとうございました
・日曜日は神戸に移動して、バドミントンの講習会
日本代表のコーチを16年務められている中西さん、筑波大学監督の吹田先生と一緒に講師を務めさせて頂きました
ジュニア期に必要な技術・技能、シニア期に必要な技術・技能の共通項や違いについて学ぶ機会になりました
一貫指導を考える上でとても重要な知識を得ることができました
学び多き、有意義な講習会になりました
・月曜日は相模原市総合選手権大会(中学生)
相模原市在住者しか出場できないため、法政クラブからは男子ダブルス1組、男子シングルス2人のみが出場しました
(結果)
男子ダブルスAクラス 優勝 ハルト・ユウキ
男子シングルスAクラス 優勝 シオン、3位 キオ
中学生はテスト空けにしては良く動けていたので安心しました
勉強とバドミントンを両立することが大切です
日頃勉強してない人がテスト前だけ勉強しても良い成績はとれませんし、テストのためだけに勉強することも意味がないようにも思います
テストが終わればすべて忘れる(短期記憶)
勉強習慣を身につけ、日々の積み重ねを大切にしていくことが大切です(長期記憶にする)
バドミントンも同様に試合前だけ練習しても勝つことはできません
日々の積み重ねが重要です
また、将来仕事をする際には複数業務を効率よく処理できる能力が求められます
ただし、マルチタスクのように同一時間内で複数業務をこなそうとすると注意散漫になり、ミスが生じ、非効率になります
複数業務を効率よくこなすためには時間で区切り(タイムブロック)、一つの業務を集中して取り組んでいくことが大切です
→タイムマネジメント能力が重要:バドミントンと勉強の両立を通して学ばせる
現実的に単にバドミントンが強いだけではお金は稼げませんし、単に教科書の内容を暗記するテストのための勉強をしても社会で活躍できる素養は身につきません
将来社会で活躍できる人材になるためには何を学ばせることが必要なのかを指導者、保護者、学校の先生も理解しなければなりません
大学受験を考えた場合、一般入試で偏差値の高い大学に入学するのはかなり大変です
高一から予備校に通って勉強したら費用も高額になります
一方、バドミントンで全国大会に出場できれば推薦で偏差値の高い大学に入学できる可能性があります
私立大学にはスポーツ推薦入試の他にもAO入試、指定校推薦入試、自己推薦入試などがあり、半数以上がこれらの入試で入学します(一般入試で入学する人は年々減っている)
推薦入試では内申点の他に特技が必要になります
ある程度の基準(内申点)を満たす必要はありますが、勉強が苦手だと思うならば特技(バドミントン)を磨いた方が大学進学の可能性は広がります
法政クラブの卒業生をみると、
ミライ→北翔大学1年
ソウ→成蹊大学1年
ユウタ(高校3年)→法政大学に入学
ハナ(高校3年)→早稲田大学に入学
みんな大学に進学してバドミントンを続けています
ジュニア→中学校→高校→大学→社会で活躍する!!
子どもたちを導いていけるように頑張ります(*^-^*)
ジュニア→中学→高校→大学→仕事(社会で活躍する!!)
進路選択に正解はなく、自分の選択をより良いものにしていくように努めていくことが大切ですが、教育なくして将来の成功は得られないようにも感じます
どのような進路を選択していくのか、将来を考えて行動していくのか、どのような仕事に就きたいのか、、、キャリア教育が重要です
昔はセカンドキャリアという観点で競技人生後のキャリアを考えていましたが、今はデュアルキャリアという考え方が主流になります
競技を続けながら将来の仕事に必要なスキルや資格を得ていくという考え方です
神奈川県は強豪チームが多く、ジュニアの競技レベルはかなり高いですが、大学で活躍する選手は少ないです
大学でバドミントンをしない理由は多様にありますが、、、中には
・厳しく指導されすぎてバドミントンに疲れて嫌いになってしまう選手
・ジュニアの時は勝てていたのに高校では勝てなくなって自信がなくなって辞めてしまう選手
・縁がなく入部を断られる選手 etc.
→例えば法政大学では練習環境(6コート使用、24人コートに入れる)を考慮して部員の人数は1学年6人程度にしています
スポーツ推薦が大半ですが、指定校推薦で入部している選手もいます
よく知らない選手、人間性に問題がある選手など、縁がなければ入部は断ります
(県外の強豪高校や大学は縁がなければ入部できない)
神奈川県のジュニアは練習環境も良く、一生懸命練習していたのに中学校では地元の中学校で競技を続けて伸び悩む選手が多くいます
Aパターン:
ジュニアの時の練習環境は良かったが、中学で練習環境が低下して伸びない選手(高校で挽回しようとしても上手くはいかない)
Bパターン:
ジュニアの時は練習環境があまり良くはなかったが、中学の練習環境が良く、競技レベルを向上させて強豪高校に進学、スポーツ推薦で大学へ
Cパターン:
ジュニア~大学まで練習環境が良い(競技レベルを向上させ続ける→日本代表へ)
Aパターンは望ましくないと考えるのに、なぜかAパターンを選択する人(保護者)が多くいます
選べるなら子どもはCパターン、Bパターンを選びますが、Aパターンを選択するのは保護者の都合が大きいように思います
・ジュニアチームのしがらみで中学から他のクラブチームには行きづらいから地元の中学校で続ける
・送迎が大変だから地元の中学校で続ける
これまでCパターンにするためには高額な費用を払って県外の強豪中学に進学するしかありませんでしたが、現在は部活動の地域移行によってクラブチームで専門的な指導を受けることができるようになりました(県外にいくよりも金銭的負担がかなり少ない)
そのメリットを活かして欲しいです
一方、中学校の部活は多感な時期における人間形成をしていく上でとても重要な役割があります
仲間を作り、初心者指導などを通してリーダーシップを育むことができます
しかし、ジュニアからやっている選手と中学から始めた選手とでは競技レベルの差が大きく、その中で上達していくのは難しいです
クラブチームでは専門的な指導を受けることができ、競技レベルを高めていくことができます
法政クラブの中学生には、学校の部活にも入ることを推奨しています
学校の部活とクラブチームの両方に所属することで、多くの仲間ができ、多様な学びが得られます
バドミントン部に入っている子が多くいますが、中には卓球部や科学部に入っている子もいます
・一番良くないのは親子のみの個人チームで続けること
→仲間も乏しく、視野も広がらず、社会性が養われません
多感な時期の中学生において、ジュニアの延長で中学校も親子でバドミントンを続けて何を学ばせたいのか危惧します
また中学生の人間的成長を得るためには、学校の部活、クラブチームのみならず、地域をあげて指導(教育)していくことも必要です
例えば中学校、クラブチームの垣根を越えて、相模原市で中学生を指導(教育)していくなど、地域をあげて多面的に指導(教育)していく体制を作りたいです
→多くの指導者、教師、保護者が関わり、子どもを育てる
アドバイスの時に「もっとクリアを高く、遠くに」、「ロブを高く、遠くに」、「サービスを高く、遠くに」など、高く、遠くに打つことを指示している場面が多くみられます
選手(子ども)からしてみれば、「高く、遠くに打てるなら打ってるよ」と思うのではないでしょうか
また、「どれくらい高く、遠くに打てば良いの?」とも思うかもしれません
コーチ、保護者に注意されないように単に高く、遠くに打っている選手もいます
この指導の仕方では論理的思考は養われません
どうしたら高く、遠くに打てるのかを考えさせることが大切です
①ラケットワークやフットワークなど、自身の態勢(フォーム)を考える
→力学的に望ましい打ち方を行います
②相手の返球を予測できているかを考える
→良い態勢で打つためには相手の返球を予測し、動き出しを早くします
③相手のストロークを制限する
→相手の技術レベルが高い場合は、良い態勢を作るために(①)、予測(②)をして動き出しを早くしようと試みても上手くいきません
その場合は低い軌道のショットを放ち、相手に意図的にスマッシュをストレートに打たせるなどして、コースを制限させて予測しやすい状況を作ります
④デセプション(惑わす)をする
→相手の動き出しを遅くして、良い態勢で打たせないようにするためにデセプションを行います
相手の態勢が悪くなれば返球も甘くなり、自身が良い態勢で打てるようになります
勝ち負けに左右されず、課題を論理的に考えさせ、試合させることで学びが得られます
単に「高く、遠くに打ちなさい」と結果主義的な指導法では子どもに学びはありません
将来、シニア期(大学生)になれば187cm(インカレ優勝した法政大学の増本選手)、2m(海外の選手)の選手と対戦することがあります
自身よりも20~30cmも身長の高い選手と対戦した場合に、どのくらい高く、遠くに打たなければいけないのかをその都度自ら考えなければいけません
論理的に考えることができない選手は、感覚的に打ちやすい高さでロブやクリアを打ち、相手に良い態勢で打たれて負けます
→ジュニア期に勝ててもシニア期では勝てない要因
論理的思考はバドミントンに限らず、社会に出て仕事をしていく上でも大切です
世の中には自身の力では変えられないことと、変えられることがあります
論理的思考はそれらを見極める視野の広さに繋がり、自身の力で変えられることに対して労力を費やすことを可能にします
バドミントンを通して何を学ぶかが重要であり、バドミントンが強いだけではお金は稼げません
子ども達が将来「社会で活躍できる」ようにするために、論理的思考を養う指導を行うことが重要です
2月15日(土)、16日(日)にかけて新人戦が開催されました
法政クラブからは17人参加
結果は女子4年生の部でリノが3位
他のメンバーは惜しくも勝ちきれず、、、入賞ならず
試合は学ぶことが多くありますね
何事も成長の糧にしていくことが大切です
今回は練習計画に問題がありました
中学生、大学生は年間計画(ピリオダイゼーション)を立てて練習内容を決めているのですが、、、小学生は年間計画を作っておらず、曖昧な状態での練習になってしまいました
(中学生) 1月上旬:専門準備期(パターン練習)、1月中旬~2月上旬:試合期(新人戦~埼玉オープン)、2月中旬~:一般準備期(フィジカル、スキル、スピードアップ)
→中学生は順調に成果を上げています
(県大会男子シングルス2位、3位、男子ダブルス2位、女子ダブルス優勝、3位、5位)
(小学生) 1月上旬:一般準備期、1月下旬:本当は専門準備期、2月中旬:本当は試合期の練習をしなければいけない所を中学生と同じ練習(一般準備期の練習)
その結果、フットワーク、ラリー力が課題に
○ノック(フィジカル、スキル、スピード)
○コート内ダッシュ(基礎的な脚力)
×フットワーク(専門的な足運び)
×パターン練習(ラリー力の強化、配球を習得する)
△ゲーム
これまでの練習内容・方法を見直し、改善していきます
→小学生も年間計画を作成します
→これまで学年ごとのグループ分けにしていましたが、混在型にします
(同じ学年の子ども同士のグループは楽しく練習できる反面、おしゃべりが多くなって練習の質が低下する)
指導者としても学び多き大会になりました
成長志向で改善していきます!!
(中学生の年間計画:ピリオダイゼーション)
中学生は埼玉オープンに参加
各県の代表チームが参加する団体戦
初日は予選リーグ
<男子>
1回戦 四街道北中学校(千葉県)に2-1で勝利
2回戦 春日部武里中学校(埼玉県)に2-1で勝利
3回戦 ふたば未来中学校(福島県)に0-3で敗退
<女子>
1回戦 小俣BJC(三重県)に0-3で敗退
2回戦 ShinShin(石川県)に0-3で敗退
3回戦 さいたま日進中学校(埼玉県)に1-2で敗退
予選リーグは男子2位、女子4位
男女ともに団体戦メンバー7人全員出場させました
明日は交流試合
各県を代表するチームと対戦でき、実りある経験ができています(*^-^*)
⇒結果詳細
ヒトの体は約60兆個の細胞からできており、その中にDNAがあります
DNAの2%を遺伝子とよび、人間を形作る設計図の役割があります
残りの98%の部分は遺伝子のon、offを決めるスイッチの役割があります
人は遺伝子のon、offを切り替えることで環境に適応し、赤道直下の暑い場所でも、酸素が少ない山の上でも、極寒の地域でも生存することができました
このような環境に依存した遺伝子変化のことをエピジェネティクスといいます
スポーツの場合はトレーニングをすることで筋肉を増やす遺伝子やバドミントンに関わる遺伝子がonになります
持ってうまれた才能、いわゆる遺伝子の有無がその人の能力を決めるのではなく、後天的な環境に依存したエピジェネティクスによって人の能力は決まります
とても重要な考え方です
勉強しないで良い成績はとれませんし、練習しないでバドミントンが上手くなることもありません
何事も日々の努力の積み重ねが大切ということは周知の事実なのに、面倒だから、大変だから、試合に出ても1回戦で負けるから、、、できない理由をあげて挑戦することをやめていく人が多くいます
何を学ぶかは本人次第
1回戦で負けても学びを得ようとすれば良い経験になります
そもそも試合にでなければ勝つこともできません
最初から挑戦することをあきらめてしまう人が多くいます
日本トップレベルの大学生を指導していて思うのは、法政クラブ(小、中学生)の子ども達にも才能ある子はたくさんいます
どうしたらもっと上手くなりますか? どうしたら試合に勝てますか?
質問されることがありますが、、、
より良い成果を出したければ現状を理解し、取り組み方、考え方を改善していく必要があります
大学生は毎日練習し、遠征に労力を惜しまず行きます
海外にも行きます
お金はかかりますが自分を成長させるために挑戦し、成功を求めて努力します
(保護者の支援があるからできる)
法政クラブの場合は大学生と同じようなことを中学生にも指導しているので、練習の質は高いです
しかし才能を伸ばして成功できるかどうかは、保護者の関わり方が影響します
子どもに意欲を持たせられるかどうかも環境に依存します
勇気づけ、可能な限り支援し、挑戦させていくことが重要です
男子はミライ(滋賀県比叡山高校)、ユウタ(宮城県ウルスラ高校)、リトヤ(宮城県ウルスラ中学校)が県外の強豪チームに進学したこともあり、意識レベルが徐々に高まってきています
これらも保護者の支援があったから挑戦できたことです
その成果として、ユウタのように法政大学にスポーツ推薦で進学できる選手も出てきました
女子は現中学生が先駆者となり、どこを目指して頑張るのか、意識レベルを高めていけるのか、これからの取り組み方で今後の成果が変わってきます
才能ある選手が多くいるので楽しみな反面、今のままでは県大会レベルで終わる可能性もあります
もっと視野を広げさせ、意識レベルを高め、才能を開花させ、全国大会で勝てるようなレベルにもっていきたいです
バドミントンを通して何を学ぶか
どのように成長させていくか
子ども達の人生がより良くなるように、指導者として学び続け、環境を改善していきます